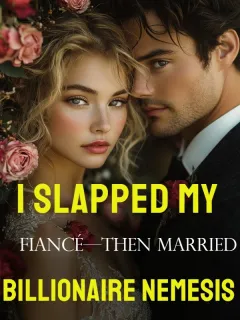The Vampire's Human Slave
Lazarus · Ongoing · 265.9k Words
Introduction
But instead, Arvin caught the eye of a monster in silk and fangs.
Now, he belongs to Prince Lester.
Not by choice. Not by vow. But by blood, contract, and the cruel twist of fate.
In the palace of knives and whispers, Arvin is paraded like a pet, touched like a prize, and watched like prey. But he isn’t meek. He isn’t obedient. If Lester wants a submissive, he’ll have to break him—and Arvin doesn’t break easy.
“Love me or hate me,” Lester murmurs, pressing him down, “either way, I’ll fuck you every night.”
But Arvin won’t be taken without a fight.
Not by a vampire. Not by a prince. Not by the devil himself.
This isn’t a romance. It’s a war of lust and dominance.
And in this castle, the one who kneels… might just survive.
🔞 Blood. Power. Pain.
Let the games begin.
Chapter 1
Arvin pov
The stench of blood is unbearable. Thick and metallic, it sticks to my skin, coats my tongue, burns my lungs.
It’s not just the blood of the others, it’s mine too, seeping from wounds I can’t afford to acknowledge. The air is thick with screams, but they’re muffled, drowned beneath the deafening pound of my own heartbeat. Chains bite into my sweat-slicked skin, my wrists are raw, my ankles are swollen from struggle.
The altar in front of me looks far too clean and luxurious for the blood bath it represents. The moon illuminates the altar, making the symbol of death look like an almost Godly construction.
More screams fill the air, the stench of blood only intensifies, making me sick to my stomach. I look to my right and try to hide the disgust - the vampires are waiting, more bloodsuckers gather around the altar.
Draped in black, their faces are concealed by those damned, grinning masks. The festival is in full swing, bodies are dragged forward, some sobbing, others too broken to resist. Some, already nothing more than headless bodies.
I hold my breath and watch. No, I force myself to watch. If I look away, I am already dead. I refuse to be one of them.
Another body is lifted onto the altar. The executioner, a creature too elegant, too refined for the horrors he inflicts, raises his hand. There’s no ceremony, no mercy, no hint of humanity all of them once had.
The ceremony hall falls silent, even the grinning vampires stop laughing as they turn their attention to the altar, watching the massacre happen. The executioner’s long nails tear through skin, crack ribs apart with ease and his fingers wrap around the still beating heart.
A raw and wet scream leaves the victim before we hear him choke on his own blood and watch in real time how life fades from his eyes. The heart, dripping blood, is tossed at the hungry vampires who fight over the organ like rabid animals.
“Next!” The low command snaps through the air, and the next moment, a hand clamps down on my shoulder, yanking me forward. It’s my turn.
“Move, worm!” The vampire snarls, digging his nails into my skin..
I let him drag me, let him think I am broken, that I am afraid, even whimper like a wounded animal for the show. But, the moment he loosens his grip to shove me onto the altar, I move.
Years of survival have taught me how to make my body a weapon. I twist, shift my weight and drive my foot into the closest one’s knee. A sharp, wet crunch, a howl of pain and he collapses. I don’t wait to see him hit the ground. I run.
“Catch him!” Someone screams.
Chaos erupts behind me, but I don’t look back. The square is a maze of nearly lifeless bodies, of the people I once called my friends, of desperate, dying souls.
I have no plan, no real idea how to escape the ceremony, but deep down, I always knew there was never going to be a real escape plan. What I have is desperation to survive and the clear understanding that if I stop running, I’ll end up like everyone before me did - dead.
Shadows move around me, they’re too fast, just a blur of motion nearby, a crowd of vampires that reach me before I can reach the edge of the square.
Their hands grasp at me, their claws tear the thin fabric of my shirt just as easily as they tear my skin. I fight like an animal, because that is what I have become. Fists, nails, teeth - I use them all.
The only thought on my mind is to survive, the only instinct that remains is to fight for my life. I keep struggling as blood splatters my face and my hands - theirs and mine, I don’t know what is what anymore and I don’t care either.
Then, claws ranke down my shoulder, splitting my flesh open easily. A heavy boot slams into my ribs, sending me sprawling.
As I collapse, dirt fills my mouth, my body aches and screams in protest. “No,” I whisper. Not like this, I can’t die like this. Not by their greedy hands.
I feel someone’s sharp nails dig into the flesh of my back but nothing happens. The whole place freezes as a presence appears out of nowhere.
The air around us immediately shifts into something thick and suffocating, so sickening, I can’t suck in a breath. It’s heavy with something I can’t name, something I know should send me fleeing, running for my life again, but the same as the vampires, I can’t move.
And then, as heavy footsteps echo around us, the vampire pulls his claw out of my flesh and all of them scatter like tiny insects.
Using my chance to escape, the window in time I know won’t last, I push myself onto my elbows despite the pain, breath tagged, eyes wild with desperation.
But before I can notice a way out, I see him.
Moonlight illuminates his frame like in a perfect movie. He’s tall, perfectly sculpted, too perfect to be real. His hair is long and dark, framing his face like a priceless painting. His eyes are the color of fresh-spilled blood; the deep red orbs lock onto mine.
My breath catches in my throat. That man, he is something equally as terrible as he is divine. And he is watching me. Not the vampires, not the blood, not the festival ceremony I’ve disrupted with my attempt to flee.. Just me.
As he steps closer, my blood runs cold. I recognize him. The man, eyeing me like his next prey is a legend. Lester, the vampiric prince - a god and a monster in one undead person.
His name is something humans don’t dare to speak aloud, like me, fearing that uttering it will curse us all with his presence.
I’m frozen on the ground, looking up at him, completely horrified as he steps towards me and stops a few steps away. The corner of his mouth twitches before his lips part. “Mine.” The word is loud, carrying over everyone present with a power I didn’t know a voice can possess.
My skin burns, I feel sick to my stomach as he reaches for me. I can’t move, but I manage to choke out a weak, “no,” and attempt to swing at him as his hand reaches closer.
He catches my wrist effortlessly. The pressure of his hold is a warning, just enough force to remind me that he could snap my bones with the slightest effort.
“Fight all you want, little human,” he murmurs. “It only makes the hunt sweeter.”
I struggle against him, but he is immovable. He watches me with amusement and something far worse flashing in those red eyes.
“Let me go!” I snarl, my nails raking across his forearm in desperation.
Lester chuckles. “Oh, but I just found you,” he whispers, “why would I ever let you go?”
Last Chapters
#203 204
Last Updated: 9/1/2025#202 203
Last Updated: 9/1/2025#201 202
Last Updated: 9/1/2025#200 201
Last Updated: 9/1/2025#199 200
Last Updated: 9/1/2025#198 199
Last Updated: 9/1/2025#197 198
Last Updated: 9/1/2025#196 197
Last Updated: 9/1/2025#195 196
Last Updated: 9/2/2025#194 195
Last Updated: 9/1/2025
You Might Like 😍
The Biker's Fate
I squeezed my eyes shut.
"Dani," he pressed. "Do you get me?"
"No, Austin, I don't," I admitted as I pulled my robe closed again and sat up. "You confuse me."
He dragged his hands down his face. "Tell me what's on your mind."
I sighed. "You're everything my parents warned me against. You're secretive, but you're also honest. I feel wholly protected by you, but then you scare me more than anyone I've ever known. You're a bad boy, but when I dated a so-called good one, he turned out to be the devil, so, yeah, I don't get you because you're not what I expected. You drive me crazier than anyone I've ever met, but then you make me feel complete. I'm feeling things I don't quite know how to process and that makes me want to run. I don't want to give up something that might be really, really good, but I also don't want to be stupid and fall for a boy just because he's super pretty and makes me come."
Danielle Harris is the daughter of an overprotective police chief and has led a sheltered life. As a kindergarten teacher, she's as far removed from the world of Harleys and bikers as you could get, but when she's rescued by the sexy and dangerous Austin Carver, her life is changed forever.
Although Austin 'Booker' Carver is enamored by the innocent Dani, he tries to keep the police chief's daughter at arm's length. But when a threat is made from an unexpected source, he finds himself falling hard and fast for the only woman who can tame his wild heart.
Will Booker be able to find the source of the threat before it's too late?
Will Dani finally give her heart to a man who's everything she's been warned about?
Accardi
“I thought you said you were done chasing me?” Gen mocked.
“I am done chasing you.”
Before she could formulate a witty remark, Matteo threw her down. She landed hard on her back atop his dining room table. She tried to sit up when she noticed what he was doing. His hands were working on his belt. It came free of his pants with a violent yank. She collapsed back on her elbows, her mouth gaping open at the display. His face was a mask of sheer determination, his eyes were a dark gold swimming with heat and desire. His hands wrapped around her thighs and pulled her to the edge of the table. He glided his fingers up her thighs and hooked several around the inside of her panties. His knuckles brushed her dripping sex.
“You’re soaking wet, Genevieve. Tell me, was it me that made you this way or him?” his voice told her to be careful with her answer. His knuckles slid down through her folds and she threw her head back as she moaned. “Weakness?”
“You…” she breathed.
Genevieve loses a bet she can’t afford to pay. In a compromise, she agrees to convince any man her opponent chooses to go home with her that night. What she doesn’t realize when her sister’s friend points out the brooding man sitting alone at the bar, is that man won’t be okay with just one night with her. No, Matteo Accardi, Don of one of the largest gangs in New York City doesn’t do one night stands. Not with her anyway.
The Prison Project
Can love tame the untouchable? Or will it only fuel the fire and cause chaos amongst the inmates?
Fresh out of high school and suffocating in her dead-end hometown, Margot longs for her escape. Her reckless best friend, Cara, thinks she's found the perfect way out for them both - The Prisoner Project - a controversial program offering a life-changing sum of money in exchange for time spent with maximum-security inmates.
Without hesitation, Cara rushes to sign them up.
Their reward? A one-way ticket into the depths of a prison ruled by gang leaders, mob bosses, and men the guards wouldn't even dare to cross...
At the centre of it all, meets Coban Santorelli - a man colder than ice, darker than midnight, and as deadly as the fire that fuels his inner rage. He knows that the project may very well be his only ticket to freedom - his only ticket to revenge on the one who managed to lock him up and so he must prove that he can learn to love…
Will Margot be the lucky one chosen to help reform him?
Will Coban be capable of bringing something to the table other than just sex?
What starts off as denial may very well grow in to obsession which could then fester in to becoming true love…
A temperamental romance novel.
I Slapped My Fiancé—Then Married His Billionaire Nemesis
Technically, Rhys Granger was my fiancé now—billionaire, devastatingly hot, and a walking Wall Street wet dream. My parents shoved me into the engagement after Catherine disappeared, and honestly? I didn’t mind. I’d crushed on Rhys for years. This was my chance, right? My turn to be the chosen one?
Wrong.
One night, he slapped me. Over a mug. A stupid, chipped, ugly mug my sister gave him years ago. That’s when it hit me—he didn’t love me. He didn’t even see me. I was just a warm-bodied placeholder for the woman he actually wanted. And apparently, I wasn’t even worth as much as a glorified coffee cup.
So I slapped him right back, dumped his ass, and prepared for disaster—my parents losing their minds, Rhys throwing a billionaire tantrum, his terrifying family plotting my untimely demise.
Obviously, I needed alcohol. A lot of alcohol.
Enter him.
Tall, dangerous, unfairly hot. The kind of man who makes you want to sin just by existing. I’d met him only once before, and that night, he just happened to be at the same bar as my drunk, self-pitying self. So I did the only logical thing: I dragged him into a hotel room and ripped off his clothes.
It was reckless. It was stupid. It was completely ill-advised.
But it was also: Best. Sex. Of. My. Life.
And, as it turned out, the best decision I’d ever made.
Because my one-night stand isn’t just some random guy. He’s richer than Rhys, more powerful than my entire family, and definitely more dangerous than I should be playing with.
And now, he’s not letting me go.
From Substitute To Queen
Heartbroken, Sable discovered Darrell having sex with his ex in their bed, while secretly transferring hundreds of thousands to support that woman.
Even worse was overhearing Darrell laugh to his friends: "She's useful—obedient, doesn't cause trouble, handles housework, and I can fuck her whenever I need relief. She's basically a live-in maid with benefits." He made crude thrusting gestures, sending his friends into laughter.
In despair, Sable left, reclaimed her true identity, and married her childhood neighbor—Lycan King Caelan, nine years her senior and her fated mate. Now Darrell desperately tries to win her back. How will her revenge unfold?
From substitute to queen—her revenge has just begun!
Badass in Disguise
"Jade, I need to check your—" the nurse began.
"OUT!" I snarled with enough force that both women backed toward the door.
Once feared by Shadow Organization that drugged me to replicate my abilities into a more controllable version, I had escaped my restraints and detonated their entire facility, ready to die alongside my captors.
Instead, I woke up in a school infirmary with women arguing around me, their voices piercing my skull. My outburst froze them in shock—clearly they hadn't expected such a reaction. One woman threatened as she left, "We'll discuss this attitude when you get home."
The bitter truth? I've been reborn into the body of an overweight, weak, and supposedly dim-witted high school girl. Her life is filled with bullies and tormentors who've made her existence miserable.
But they have no idea who they're dealing with now.
I didn't survive as the world's deadliest assassin by allowing anyone to push me around. And I certainly won't start now.
The mafia princess return
My Possessive Alpha Twins For Mate
My drunk stepfather remained indifferent, his weight suffocating, making it hard to breathe as my heart raced.
Suddenly, the door slammed open, and two figures burst in.
"Get off her!" a deafening roar echoed.
I didn't expect the twin brothers who'd bullied me at school to come charging in like gods to save me.
After my grandmother passed, I had to move in with my mom and stepdad, who treated me like a servant. I prayed every day for my 18th birthday to come, so l could leave and escape this broken home.
However, on my first day at my new school, l encountered the legendary twins everyone feared.
To make matters worse, the Moon Goddess revealed they were both my mates!
After helping me out with my stepdad, my twin mate cornered me, played with my hair, and whispered possessively, "You belong to us, our little mate..."
The Pack: Rule Number 1 - No Mates
"Let me go," I whimper, my body trembling with need. "I don't want you touching me."
I fall forward onto the bed then turn around to stare at him. The dark tattoos of Domonic's chiseled shoulders, quiver and and expand with the heave of his chest. His deep dimpled smile is full of arrogance as he reaches behind himself to lock the door.
Biting his lip, he stalks toward me, his hand going to the seam of his pants and the thickening bulge there.
"Are you sure you don't want me to touch you?" He whispers, untying the knot and slipping a hand inside. "Because I swear to God, that is all I have been wanting to do. Every single day from the moment you stepped in our bar and I smelled your perfect flavor from across the room."
New to the world of shifters, Draven is human on the run. A beautiful girl who no one could protect. Domonic is the cold Alpha of the Red Wolf Pack. A brotherhood of twelve wolves that live by twelve rules. Rules which they vowed could NEVER be broken.
Especially - Rule Number One - No Mates
When Draven meets Domonic, he knows that she is his mate, but Draven has no idea what a mate is, only that she has fallen in love with a shifter. An Alpha that will break her heart to make her leave. Promising herself, she will never forgive him, she disappears.
But she doesn’t know about the child she’s carrying or that the moment she left, Domonic decided rules were made to be broken - and now will he ever find her again? Will she forgive him?
Omega Bound
Thane Knight is the alpha of the Midnight Pack of the La Plata Mountain Range, the largest wolf shifter pack in the world. He is an alpha by day and hunts the shifter trafficking ring with his group of mercenaries by night. His hunt for vengeance leads to one raid that changes his life.
Tropes:
Touch her and die/Slow burn romance/Fated Mates/Found family twist/Close circle betrayal/Cinnamon roll for only her/Traumatized heroine/Rare wolf/Hidden powers/Knotting/Nesting/Heats/Luna/Attempted assassination
THE ALPHA'S NANNY.
Lori Wyatt, a shy, broken twenty two year old with a dark past is given the deal of a lifetime when she is asked to be the nanny of a newborn who lost her mother at childbirth. Lori accepts, eager to get away from her past.
Gabriel Caine is the Alpha of the revered Moon fang pack and the CEO of Caine Inc. A drunken one night stand leads to the birth of his daughter and he finds her a nanny following the death of her mother. When he meets Lori, he finds out that she is his mate and vows to protect her from his enemies.
The two of them cannot stop the instant attraction between them. Lori, who believes she is unworthy of love, cannot explain why the powerful billionaire is after her and Gabriel who is totally smitten with her is unsure of how to be totally honest with Lori about him being a werewolf.
Fate has brought them together and now together they must fight for their love, amidst the conflicts between packs and secrets that Lori’s past holds.
Will their love survive?
Mr. Ryan
He came closer with a dark and hungry expression,
so close,
his hands reached for my face, and he pressed his body against mine.
His mouth took mine eagerly, a little rudely.
His tongue left me breathless.
“If you don't go with me, I'll fuck you right here.” He whispered.
Katherine kept her virginity for years even after she turned 18. But one day, she met an extremely sexual man Nathan Ryan in the club. He had the most seductive blue eyes she has ever seen, a well-defined chin, almost golden blonde hair, full lips, perfectly drawn, and the most amazing smile, with perfect teeth and those damn dimples. Incredibly sexy.
She and he had a beautiful and hot one-night stand...
Katherine thought she might not meet the man again.
But fate has another plan
Katherine is about to take on the job of assistant to a billionaire who owns one of the biggest companies in the country and is known to be a conquering, authoritative and completely irresistible man. He is Nathan Ryan!
Will Kate be able to resist the charms of this attractive, powerful and seductive man?
Read to know a relationship torn between anger and the uncontrollable desire for pleasure.
Warning: R18+, Only for mature readers.