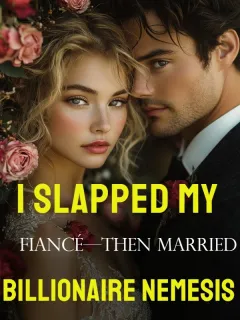The Carrero Effect trilogy
Leanne Marshall · Ongoing · 447.1k Words
Introduction
Chapter 1
I smooth my hands down my pencil skirt and gray tailored jacket before touching up my dark lipstick in the hall mirror with a look of resignation. My eyes scan and check my tawny hair is neat and sleek in its high bun, and I scrutinize my reflection again to make sure it’s precise. Sighing once more, I take a steadying breath, trying to ready myself, pushing down the gnawing ache of anxiety and nerves deep inside my gut.
I’ll do.
I look as good as I know I’m capable of, and I’m mildly satisfied with what I see before me: a cool, efficient image of cold poise and gray tailoring that exudes authority, with no hint of the turmoil of emotion inside me. I narrow my eyes to look for any flaws in my immaculate armor, any stray hairs, specks of dust, or creased fabric and find none.
I’ve never been a lover of my own reflection with my youthful appearance, cool blue eyes, and pouting lips, but nothing is out of place, and I look right for my new role as personal assistant to my very high-profile boss. I look professional and capable on the outside, which I guess matters: calm and uncompromising with every detail in place and clothes flawlessly neat. I have always been good at shielding the truth about how I feel inside.
I slide on my stilettos in a slow, careful motion, keeping my balance with one hand on the wall. Hearing the movement in the room behind me, I check the mirror in response.
“Morning, Ems. God, you look professional as always.” Sarah stifles a yawn as she wanders from her room and rubs her eyes with the back of her fist childishly as I watch her in the reflection behind me. It’s unusual for her to be up this early on her day off; Sarah’s never been a lover of mornings for as long as I’ve known her.
She’s wearing her baggy pink housecoat, and her messy, short, bleached blonde hair is sticking up at all angles from her head, casually loveable as always. I am warmed with affection for that bundle of happy energy. Her bright blue eyes are heavy with early morning fatigue, and she’s watching me closely with a silly smile on her face. A little too closely for my liking.
“Good morning, Sarah,” I smile lightly, trying to ignore how she’s looking at me, and straighten up to stand tall. I’m ever conscious of my grace and mannerisms under scrutiny, even in front of her, and I push out the sense of tightness from my nerves today, swallowing down the listlessness, trying extremely hard to curb the swirling of my stomach. I turn, lifting my briefcase from the floor, and head forward into our open-plan apartment.
“Remember, you need to be here for ten o’clock … the boiler repair,” I remind her as she shuffles behind me to the living room area, trying to distract her from the open gawking she seems to be doing. Running through my schedule in my head like a mental checklist gives me something else to think about besides my uneasiness today.
“I know. I know! You left me a memo on the fridge, remember?” she giggles childishly and throws me a patient look, raising a brow with an almost indulgent expression. She looks much younger than her age, and sometimes I forget we went to school together. I’m more like her guardian than her roommate nowadays, but maybe I always was, if I am being honest. I sigh again, pushing down the tight knot of apprehension growing inside and giving her a small bravado smile.
“Don’t forget.” I sound stern, but she doesn’t react; she’s used to my severe tone and the endless organization of our lives. She knows this is the way I do things; my need to control and have everything just so makes me feel more capable.
“I won’t. I swear. I’m not working until tonight, so I’m going to stick around and chillax … watch some back-to-back Netflix.” She moves lazily through the bright white and gray kitchen to my side and begins making herself a coffee. With another sleepy bright smile, she lifts the mug I washed earlier this morning from the rack for herself. I watch her casual, confident movements around the space and her domain when she’s at home, giving me a sense of calm.
Sarah was always good at making me feel a little saner when I needed it, never aware of how I drew from that uncomplicated, relaxed manner of hers when I had to ground myself.
“I’m going to work.” I walk steadily into the small hall by the side of the bar, which juts out into the lounge and lift the few open letters from the counter I’ve yet to deal with today. I know that I’m lingering and acting indecisively compared to my usual efficient routine. Normally I’d already be walking to the subway station, despite being early.
“Oh, here,” Sarah says, sliding a white envelope out from behind the toaster and holding it out expectantly for me to take, a blank look on her face. “Before I forget … I know you’ve probably already taken care of them, as usual.” Her sparkling eyes flash at me with affectionate amusement.
“What is it?” I look at the long envelope, taking it from her slowly with careful fingers, eyeing it up with a frown, seeing no writing on the front.
“My half of the utilities and the rent. I got paid early.” She smiles brightly and sets about making herself breakfast, pulling a loaf of bread open and sliding slices into the toaster.
“Right. And yes, I’ve taken care of it already … thank you.” I take it and slide it into my bag to bank at lunch, mentally noting down a memo to do so. I ritually pay our bills at the start of every month when I’m paid; having a very good wage in a great company with many perks makes it effortless to make sure we are always up to date.
“No surprise there then,” she mumbles and throws me another affectionate look, all cute eyes and gentle sighs as she regards me with a sideways glance that I clearly catch. I shake my head at her, fully aware that she prefers that I take control of our living expenses and always has. Taking care of things is how I like it; it gives me purpose, control, and a focus in my life that I so desperately need to thrive. She’s never been good with money, and I doubt she would remember to pay the rent on time without my ever-efficient presence.
“I won’t be home until six o’clock, Sarah. I presume you’ll be at work by then, so have a wonderful day.” I move away from the breakfast bar and head for the main door of our apartment, lifting my warm jacket as I pass the dining table, and turn with a smile when I reach the dark slate door.
“Oh, wait … good luck on meeting your super-hot boss for the first time, Miss Anderson!” she beams at me excitedly, raising her eyebrows, leaning out across the countertop so all I can see is her head popping out from the kitchen at a funny angle. She looks messy but cute and far too awake for her today. I smile back emptily, not wanting to give my feelings away or show any weakness.
“Thanks.” My face heats slightly with the rise of nerves hitting my stomach hard again, but I ignore the sensation, swallowing it all down with the expertise of a seasoned actress.
“Are you nervous?” she probes with a little furrow of her brow, still leaning out a little too far to watch me adjust my briefcase handle and pull my outside jacket on over my suit. I frown back at her question, the tightening knot in my stomach intensifying somewhat, but I shake my head ‘no’ in reply. If I admit it to her, then I admit it to myself, my nerves will get the better of me, and I’ll lose my edge.
That wouldn’t do at all.
“Of course, you’re not. You never are!” she adds quickly with a grin and slides back into her little culinary world, oblivious to anything amiss in my behavior today. I smile again as I watch her recede and turn with a wave of my fingertips before heading out the door on my mission to get to work.
Sweet Sarah. She’s so sure of my capabilities and calm, outward confidence that I sometimes wonder if she even remembers the old me at all, if she even associates me with the girl I was when we met so many years ago?
I close the door behind me quietly, holding onto the handle for a second as I take a deep, steadying breath and take a moment to be still, refusing to let emotion get the better of me and crack my armor. Looking down at the cool silver knob as a way of calming myself once more, I steady that creep of inner nerves and push down all my anxiety and fears.
I can do this.
It’s what I’ve been working so hard for; finally, my abilities are being recognized after years of hard work and climbing the corporate ladder. I need to push down the inner doubts and the final traces of my adolescent Emma to focus on the tasks ahead of me and the responsibilities I’ll be taking on after today. It is heady and overwhelming, but I steel my nerves inwardly, stilling my hands against me as I’ve practiced a million times in the last ten years. Every day I’ve worked toward this person I’ve become, this cool and confident persona known as Emma Anderson.
It takes a moment to be able to walk away from the door, but as I do, the armor slides up, and the mask fully connects with my face. Each step strengthens my resolve, back to my usual practiced demeanor and inner me, finding the willpower and continued strength to pull this off day after day. I head to the subway station.
Last Chapters
#279 279
Last Updated: 1/7/2025#278 278
Last Updated: 1/7/2025#277 277
Last Updated: 1/7/2025#276 276
Last Updated: 1/7/2025#275 275
Last Updated: 1/7/2025#274 274
Last Updated: 1/7/2025#273 273
Last Updated: 1/7/2025#272 272
Last Updated: 1/7/2025#271 271
Last Updated: 1/7/2025#270 270
Last Updated: 1/7/2025
You Might Like 😍
The Biker's Fate
I squeezed my eyes shut.
"Dani," he pressed. "Do you get me?"
"No, Austin, I don't," I admitted as I pulled my robe closed again and sat up. "You confuse me."
He dragged his hands down his face. "Tell me what's on your mind."
I sighed. "You're everything my parents warned me against. You're secretive, but you're also honest. I feel wholly protected by you, but then you scare me more than anyone I've ever known. You're a bad boy, but when I dated a so-called good one, he turned out to be the devil, so, yeah, I don't get you because you're not what I expected. You drive me crazier than anyone I've ever met, but then you make me feel complete. I'm feeling things I don't quite know how to process and that makes me want to run. I don't want to give up something that might be really, really good, but I also don't want to be stupid and fall for a boy just because he's super pretty and makes me come."
Danielle Harris is the daughter of an overprotective police chief and has led a sheltered life. As a kindergarten teacher, she's as far removed from the world of Harleys and bikers as you could get, but when she's rescued by the sexy and dangerous Austin Carver, her life is changed forever.
Although Austin 'Booker' Carver is enamored by the innocent Dani, he tries to keep the police chief's daughter at arm's length. But when a threat is made from an unexpected source, he finds himself falling hard and fast for the only woman who can tame his wild heart.
Will Booker be able to find the source of the threat before it's too late?
Will Dani finally give her heart to a man who's everything she's been warned about?
The Prison Project
Can love tame the untouchable? Or will it only fuel the fire and cause chaos amongst the inmates?
Fresh out of high school and suffocating in her dead-end hometown, Margot longs for her escape. Her reckless best friend, Cara, thinks she's found the perfect way out for them both - The Prisoner Project - a controversial program offering a life-changing sum of money in exchange for time spent with maximum-security inmates.
Without hesitation, Cara rushes to sign them up.
Their reward? A one-way ticket into the depths of a prison ruled by gang leaders, mob bosses, and men the guards wouldn't even dare to cross...
At the centre of it all, meets Coban Santorelli - a man colder than ice, darker than midnight, and as deadly as the fire that fuels his inner rage. He knows that the project may very well be his only ticket to freedom - his only ticket to revenge on the one who managed to lock him up and so he must prove that he can learn to love…
Will Margot be the lucky one chosen to help reform him?
Will Coban be capable of bringing something to the table other than just sex?
What starts off as denial may very well grow in to obsession which could then fester in to becoming true love…
A temperamental romance novel.
I Slapped My Fiancé—Then Married His Billionaire Nemesis
Technically, Rhys Granger was my fiancé now—billionaire, devastatingly hot, and a walking Wall Street wet dream. My parents shoved me into the engagement after Catherine disappeared, and honestly? I didn’t mind. I’d crushed on Rhys for years. This was my chance, right? My turn to be the chosen one?
Wrong.
One night, he slapped me. Over a mug. A stupid, chipped, ugly mug my sister gave him years ago. That’s when it hit me—he didn’t love me. He didn’t even see me. I was just a warm-bodied placeholder for the woman he actually wanted. And apparently, I wasn’t even worth as much as a glorified coffee cup.
So I slapped him right back, dumped his ass, and prepared for disaster—my parents losing their minds, Rhys throwing a billionaire tantrum, his terrifying family plotting my untimely demise.
Obviously, I needed alcohol. A lot of alcohol.
Enter him.
Tall, dangerous, unfairly hot. The kind of man who makes you want to sin just by existing. I’d met him only once before, and that night, he just happened to be at the same bar as my drunk, self-pitying self. So I did the only logical thing: I dragged him into a hotel room and ripped off his clothes.
It was reckless. It was stupid. It was completely ill-advised.
But it was also: Best. Sex. Of. My. Life.
And, as it turned out, the best decision I’d ever made.
Because my one-night stand isn’t just some random guy. He’s richer than Rhys, more powerful than my entire family, and definitely more dangerous than I should be playing with.
And now, he’s not letting me go.
Badass in Disguise
"Jade, I need to check your—" the nurse began.
"OUT!" I snarled with enough force that both women backed toward the door.
Once feared by Shadow Organization that drugged me to replicate my abilities into a more controllable version, I had escaped my restraints and detonated their entire facility, ready to die alongside my captors.
Instead, I woke up in a school infirmary with women arguing around me, their voices piercing my skull. My outburst froze them in shock—clearly they hadn't expected such a reaction. One woman threatened as she left, "We'll discuss this attitude when you get home."
The bitter truth? I've been reborn into the body of an overweight, weak, and supposedly dim-witted high school girl. Her life is filled with bullies and tormentors who've made her existence miserable.
But they have no idea who they're dealing with now.
I didn't survive as the world's deadliest assassin by allowing anyone to push me around. And I certainly won't start now.
The mafia princess return
My Possessive Alpha Twins For Mate
My drunk stepfather remained indifferent, his weight suffocating, making it hard to breathe as my heart raced.
Suddenly, the door slammed open, and two figures burst in.
"Get off her!" a deafening roar echoed.
I didn't expect the twin brothers who'd bullied me at school to come charging in like gods to save me.
After my grandmother passed, I had to move in with my mom and stepdad, who treated me like a servant. I prayed every day for my 18th birthday to come, so l could leave and escape this broken home.
However, on my first day at my new school, l encountered the legendary twins everyone feared.
To make matters worse, the Moon Goddess revealed they were both my mates!
After helping me out with my stepdad, my twin mate cornered me, played with my hair, and whispered possessively, "You belong to us, our little mate..."
Omega Bound
Thane Knight is the alpha of the Midnight Pack of the La Plata Mountain Range, the largest wolf shifter pack in the world. He is an alpha by day and hunts the shifter trafficking ring with his group of mercenaries by night. His hunt for vengeance leads to one raid that changes his life.
Tropes:
Touch her and die/Slow burn romance/Fated Mates/Found family twist/Close circle betrayal/Cinnamon roll for only her/Traumatized heroine/Rare wolf/Hidden powers/Knotting/Nesting/Heats/Luna/Attempted assassination
Mr. Ryan
He came closer with a dark and hungry expression,
so close,
his hands reached for my face, and he pressed his body against mine.
His mouth took mine eagerly, a little rudely.
His tongue left me breathless.
“If you don't go with me, I'll fuck you right here.” He whispered.
Katherine kept her virginity for years even after she turned 18. But one day, she met an extremely sexual man Nathan Ryan in the club. He had the most seductive blue eyes she has ever seen, a well-defined chin, almost golden blonde hair, full lips, perfectly drawn, and the most amazing smile, with perfect teeth and those damn dimples. Incredibly sexy.
She and he had a beautiful and hot one-night stand...
Katherine thought she might not meet the man again.
But fate has another plan
Katherine is about to take on the job of assistant to a billionaire who owns one of the biggest companies in the country and is known to be a conquering, authoritative and completely irresistible man. He is Nathan Ryan!
Will Kate be able to resist the charms of this attractive, powerful and seductive man?
Read to know a relationship torn between anger and the uncontrollable desire for pleasure.
Warning: R18+, Only for mature readers.
Alpha Nicholas's Little Mate
What? No—wait… oh Moon Goddess, no.
Please tell me you're joking, Lex.
But she's not. I can feel her excitement bubbling under my skin, while all I feel is dread.
We turn the corner, and the scent hits me like a punch to the chest—cinnamon and something impossibly warm. My eyes scan the room until they land on him. Tall. Commanding. Beautiful.
And then, just as quickly… he sees me.
His expression twists.
"Fuck no."
He turns—and runs.
My mate sees me and runs.
Bonnie has spent her entire life being broken down and abused by the people closest to her including her very own twin sister. Alongside her best friend Lilly who also lives a life of hell, they plan to run away while attending the biggest ball of the year while it's being hosted by another pack, only things don't quite go to plan leaving both girls feeling lost and unsure about their futures.
Alpha Nicholas is 28, mateless, and has no plans to change that. It's his turn to host the annual Blue Moon Ball this year and the last thing he expects is to find his mate. What he expects even less is for his mate to be 10 years younger than him and how his body reacts to her. While he tries to refuse to acknowledge that he has met his mate his world is turned upside down after guards catch two she-wolves running through his lands.
Once they are brought to him he finds himself once again facing his mate and discovers that she's hiding secrets that will make him want to kill more than one person.
Can he overcome his feelings towards having a mate and one that is so much younger than him? Will his mate want him after already feeling the sting of his unofficial rejection? Can they both work on letting go of the past and moving forward together or will fate have different plans and keep them apart?
Mated by Contract to the Alpha
William—my devastatingly handsome, wealthy werewolf fiancé destined to become Delta—was supposed to be mine forever. After five years together, I was ready to walk down the aisle and claim my happily ever after.
Instead, I found him with her. And their son.
Betrayed, jobless, and drowning in my father's medical bills, I hit rock bottom harder than I ever imagined possible. Just when I thought I'd lost everything, salvation came in the form of the most dangerous man I'd ever encountered.
Damien Sterling—future Alpha of the Silver Moon Shadow Pack and ruthless CEO of Sterling Group—slid a contract across his desk with predatory grace.
“Sign this, little doe, and I'll give you everything your heart desires. Wealth. Power. Revenge. But understand this—the moment you put pen to paper, you become mine. Body, soul, and everything in between.”
I should have run. Instead, I signed my name and sealed my fate.
Now I belong to the Alpha. And he's about to show me just how wild love can be.
The Son of Red Fang
Alpha Cole Redmen is the youngest of six born to Alpha Charles and Luna Sara Mae, leaders of the Red Fang pack. Born prematurely, Alpha Charles rejected him without hesitation as weak and undeserving of his very life. He is reminded daily of his father’s hatred for him paving the way for the rest of his family to become the same.
By adulthood, his father’s hatred and abuse towards him has spilled over into the rest of the pack making him the scapegoat for those with the sadistic need to see him suffer. The rest are simply too afraid to even look his way leaving him little in the way of friends or family to turn to.
Alpha Demetri Black is the leader of a sanctuary pack known as Crimson Dawn. It’s been years since a wolf has made their way to his pack via the warrior’s prospect program but that doesn’t mean he’s not looking for the tell tale signs of a wolf in need of help.
Malnourished and injured upon his arrival, Cole’s anxious and overly submissive demeanor lands him in the very situation he’s desperate to avoid, in the attention of an unknown alpha.
Yet somehow through the darkness of severe illness and injury he runs into the very person he’s been desperate to find since he turned eighteen, his Luna. His one way ticket out of the hell he’s been born into.
Will Cole find the courage needed to leave his pack once and for all, to seek the love and acceptance he’s never had?
Content Warning: This story contains descriptions of mental, physical and sexual abuse that may trigger sensitive readers. This book is intended for adult readers only.
Goddess Of The Underworld: The Goddess Legacy (Book One)
When the veil between the Divine, the Living, and the Dead begins to crack, Envy is thrust beneath with a job she can’t drop: keep the worlds from bleeding together, shepherd the lost, and make ordinary into armor, breakfasts, bedtime, battle plans. Peace lasts exactly one lullaby. This is the story of a border pup who became a goddess by choosing her family; of four imperfect alphas learning how to stay; of cake, iron, and daylight negotiations. Steamy, fierce, and full of heart, Goddess of the Underworld is a reverse harem, found-family paranormal romance where love writes the rules and keeps three realms from falling apart.